
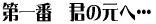
何故・・・何故、こんな哀しい結末なんだろう・・・
純粋に自分の信念を貫いた人が死んでしまうなんて・・・
何よりも死んでほしくない人が逝ってしまった・・・・・・
生きてほしかった、でも物語上仕方のないことなのかもしれない
もし・・・もしも、違う未来があるとしたら・・・
ここは死した魂が集う『尸魂界』にある
私達死神の住む霊屋『瀞霊廷』
そう、私は死神。この瀞霊廷を護る護廷十三隊の番外、零番隊隊員
そして特殊部門の『技術開発局』局員でもある
現世が好きな隊長と、隊長の恋人で現世かぶれの局長
その影響で私は現世の物を触ったり見たりする機会が多かった
ある時、隊長が現世から持ち帰ってきた本を薦められて読んだ
それは漫画というものでタイトルは『DEATH NOTE』
私達とは違う現世の人達が思い描く死神が登場する内容だった
その中で一番気になった登場人物の『L』・・・
彼の信念、彼の言う正義、彼の生い立ち、全てを知りたいと思った
気付けばいつも彼の事を考えている自分がいた
それはまるで彼に恋をしているかのように・・・
今日も隊長から譲ってもらったデスノートを読み終わって
なんとも言えない気持ちで布団に入り眠りについた
深く深く意識が落ちていく、そんな感覚に違和感を覚える
そして聴こえてくる子供の泣き声、子供・・・というよりは赤ん坊の泣き声
気付くと私は教会のような所に立っていた
目の前には火がついたように泣きじゃくっている赤ん坊
『ここは・・・?それに、私・・・自分の部屋にいたはずなのに・・・
あぁ、泣かないで・・・・・・どうしてこんな所に・・・もしかして、捨て子?』
そっと頭を撫でると軟らかい感触
魂魄のはずの私が何故触れる事ができるのか解らないけど
そっと抱き上げると暖かい重みが腕に伝わる
『泣かないで・・・いい子だね・・・』
大声をあげて泣いている赤ん坊に微笑みかけあやしていると
暫くしゃくりあげて、安心してくれたのか今は静かに眠っている
私はいつまでもここに居るわけにはいかない
どうしようかと考えをめぐらせた時、この教会に住んでいる人だろうか
人の気配を感じたので腕の中で眠っているこの子をそっと椅子の上に寝かせると
私の意識は途切れ、今度は浮上していく
気付けば私は見覚えのある自分の部屋で布団の中にいた
「夢・・・?」
夢にしては現実味のある・・・あの子の髪の軟らかさも温かさも覚えている
不思議な体験・・・・・・
それから数日してまた同じように意識が落ちていく
今回、聴こえてくるのは子供の泣き声
それも押し殺したようなくぐもった声
視界が開けるとそこは子供部屋のようだった
声の主を探すとベッドの上で毛布に包まっている子供
あの時の赤ん坊と同じ霊圧
ということは、目の前で毛布に包まっているのは
あの時の子供・・・?時の流れが違うの?
不思議に思いながら辺りを見回すと、子供部屋にしては殺風景な部屋
私はそっとベッドに近付き毛布から覗く黒髪に触れようとした
その時、自分の身体が透けていることに気付いた
あの時のように触れる事はできないみたいだけど
震える髪を撫でるようにすれば、涙に濡れた黒い瞳が私を見上げた
『!?・・・・・・私が見えるの・・・?』
この子の霊圧からすると私の姿は見えないはず
それ以前に私自身が透けて見えるということは思念体のようなものかもしれない
「・・・?」
毛布から顔を出して辺りを不思議そうに見回している
この子・・・っ、面影が・・・まるであの漫画のデスノートの『L』にそっくり
まさか・・・ね・・・・・・
『子供は感受性が豊かだから何か感じるのかな・・・?』
涙の痕が残るふっくらとした頬を撫でると、びくりと反応する
大きな瞳をさらに大きく見開くから瞳が零れ落ちそうに見える
口を真一文字にして辺りをきょろきょろと見回している
その姿が可愛くて微笑いが零れる
ふと時計を見れば深夜である事がわかる
時間は私の居た尸魂界と同じなのかな・・・?
『もう眠りなさい、君が眠るまで傍にいるから・・・』
Lによく似た少年は眠りに落ちる前のほんの一瞬
私と視線を合わせた
「Who・・・are・・you・・・?」
『え・・・えい、ご・・・?』
少年が完全に眠ると同時に私の意識も途切れた
目覚めるとあの日と同じように自分の部屋で
あの少年の感触が残っている
夢にしては現実味がありすぎる・・・一体なにを意味しているのか・・・
二度ある事は三度あるというし・・・これが何度かあるようなら
隊長に相談してみようかな
そう考えていた数週間の間に何度もあの少年の元へ私は現れた
少年は成長している時もあったし変わらない時もあった
そしてその少年は成長する毎にあの『L』にそっくりになっていく
それに会う度に泣いていたり寂しそうにしていた
『孤独』を背負っている、そんな感じがした
その事を隊長に相談すると恋人である喜助さん・・・局長となにやら話し始めた
「ねぇ、・・・貴女は並行世界、もしくは並行宇宙、並行時空ともいうわね。それを信じる?」
「それは・・・いわゆるパラレルワールドというやつですか?」
「そう、タイムトラベルっていう考えもあるけど・・・
あの漫画の登場人物にそっくりなんでしょ?っていうか本人でしょ」
「はぁ・・・でも、ただこの世界で私の思念体が移動しているだけというのは・・・」
「それなら判るはずなのよ、霊圧の揺れがあるからね」
「そうですか・・・でもタイムトラベルじゃないって・・・」
「それはっすねぇ、タイムトラベルは現時点で
全く実用化のめどは立っていないんス、けど理論物理学などの研究によりますと
必ずしも「時間」は固定的なものであるとは限らない
従って『タイムトラベル』は絶対不可能なものだとも断言できない
といわれてます・・・が、どちらかと言うと物理学の世界で
理論的な可能性が語られてる並行世界の方が現実味があるんっスよ」
人差し指を立てて力説する喜助さんの目が少し怖い
それに隊長の何か企んでますというような顔も怖い・・・
・・・・・・ 嫌な予感がする・・・
そんなやり取りをしてから、何度も何度もあの少年の元へ現れる私
ある日、少年は眠りに落ちる寸前に贈り物をくれた(たぶん・・・)
それは器用に編んだ革紐で包んだビー球
綺麗なガラス球の中には『L』の文字に見える飾りがひとつ
やっぱり彼はあの『L』なのかな・・・
隊長、局長のいう並行世界が現実味を帯びてくる
私はお礼に彼の枕元に小瓶に入った金平糖を置いておいた
それからずっと彼から貰ったビー球をアクセサリー代わりに
ブレスレットにして身につけていた
毎日身につけていたから、思っていた通り革紐は切れてしまった
私はそれに手を加えてチョーカーにして今も身につけている
初めて彼に会った時から随分と時が流れたような気がする
少年だった彼は青年になっていく
もし彼が本当に『L』なのだとしたら、彼の死の時が近付いてくる・・・
私はただこうして見ている事しかできないのだろうか・・・
彼を助けたいなんて烏滸がましい事は言わない
ただ、死なないで生きてほしい
そう願うことしか私にはできない・・・
彼の声を聞くことが出来ても、私の声は彼には聞こえないのだから
Lのあの結末を思い出す度に沈んでいく気持ちを抑えて
呼び出されて技術開発局に訪れた私を待っていたのは
満面の笑みの局長と隊長・・・・・・局長である喜助さんは判るんだけど
なぜ隊長まで・・・?しかもお二人の満面の笑みが凄く胡散臭い・・・
「あの・・・局長がここにいるのは判るんですけど・・・
隊長、なにをしているんですか?隊舎で副隊長達が探してますよ、きっと・・・」
「まぁまぁ、気にしない気にしない。こっち来て、」
「いや、気にしてくださいよ。で、なんなんですか?」
「完成したんスよ」
「は?何がですか?」
「「時空転移装置!!」」
「・・・・・・時空・・・転移、装置・・・ってはぁ !?
ちょ・・・お二人とも何考えてるんですか!?ってか嫌な予感しかしないんですけど!?」
逃げ腰になる私の両肩をがっしりと掴む上司二人
美形なお二人の最高の微笑みが悪魔の微笑みに見える・・・
「造ったからには」
「実験をしないといけないんスよ」
「それで思念体とはいえ時空を渡った可能性のある
にお願いしようと思って、ね?」
「ね?ってそんな可愛く首傾げて言われても困りますぅぅぅっ」
「変えたくない?の心を沈ませる原因の未来を・・・」
「え・・・?」
「例えば、この漫画が示すのがが度々あう彼の未来だとしても
それは彼の未来の一つでしかない、これは物語の一つなのだから
だから、あなたという存在がこの世界に入る事によって
未来はいくらでも変わる、決まりきった運命などないのよ」
「どうします?さん、今なら喜助印の特性義骸を付けてあげるっスよ」
局長はにっこりと笑いながら既に私の義骸を装置の中に入れている
「運命を変えたくないって言ったら嘘になります・・・けど
・・・・・・っていうか、拒否権ってあるんですか?」
「「ないに決まってるじゃない(っすか)」」
「や、やっぱり〜〜〜〜〜っ」
ぐいぐいと装置の中に押し込まれて
にっこりと悪魔の笑みを浮かべる上司二人を見る
「逝ってらっしゃい、さん」
「がんばるのよ?」
「字が、字が違いませんか!?喜助さんっっ」
ピッと機械音がしたと思ったら目の前がスパークした
まさか・・・実験台にされるなんて・・・っ
行き先の説明とか何もなかったんですけど!?
本当にあのデスノートの世界に転移できるのか・・・
あのお二人が造ったものだから機械に対しての不安はないけど
着いた先での不安はてんこ盛り
っていうか、私が帰らなきゃ実験に成功したのかどうかさえも判らないんじゃ・・・?
なんて考えていると急に浮遊感と眩しい光に襲われる
霊子を固めて足場を安定させ光が治まったのを感じると
そっと目をあけると、そこは見た事もない煌びやかな場所だった



